「この薬って胃薬だけど、あたまには影響ないのかな」
そんなことを考えたことがある好奇心のあるかたは、いませんか?
[show_more more=”続きを読む”
less=”閉じる”color=”#2E9AFE”]
心配しないでください。頭には、必要じゃないものが血流に乗って流れていかないようにする血液脳関門(BBB: blood brain barrier)というバリアが血液と脳の物質交換を制限しています。
このバリアがあることで、必要なものを選んで脳のなかに流れるように調節しています。
血液内皮細胞のS1P1受容体が脳血流を調節する
コーネル大学の研究者らは、今回のマウスの実験で、血管のうちがわにある血液内皮細胞のS1P1受容体に働きかけることで、今まで通過できなかった小さな分子を選択的に通過できるということがわかりました。
S1P1受容体は、血管内皮細胞の間のつながりを強くすることで知られています。
小さな分子を選択的に通過できるため、脳に与えるダメージもありませんでした。
脳血流を調節するタンパク質が新たな治療ターゲットに
今までもこの分野は多くの研究がされていて、Cldn5、Ocln、最近ではLSR、GPR116といったタンパク質が血液脳関門を通過しやすくすることが分かっています。
今後より研究が進んでいくことで、脳の中に流れていく薬の量を調節し、神経病、精神領域の治療の発展につながっていくのではないかと期待されます。
参照:PNAS
301 Moved Permanently
[/show_more]

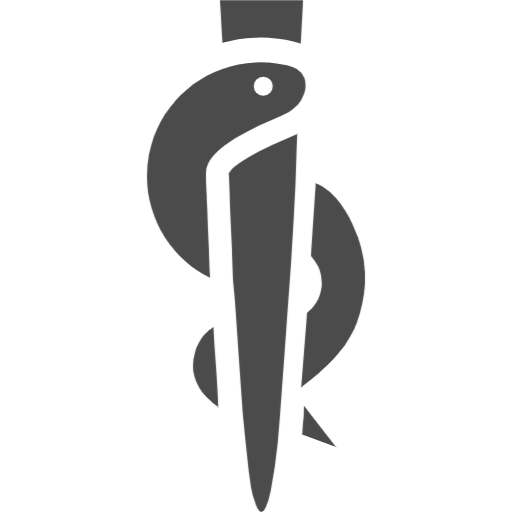

コメント