続きです。
76 看護師Aが患者Bの点滴ボトルに薬剤を注入しているとき、新人看護師から患者Cについて相談を受けた。看護師Aが作業を中断し新人看護師に対応した後、患者Bの点滴ボトルに患者Cの名前を記入するというヒヤリハットが発生した。
この病棟の看護師長が行う再発防止策で適切なのはどれか。
- 看護師Aに対策を考えさせる。
- 看護師Aを注射の業務から外す。
- 作業中断の対策を病棟チームで検討する。
- 再発防止カンファレンスを1か月後に計画する。
「ヒヤリ・ハット」の事例を記録し蓄積または共有することによって、医療事故の防止・医療安全に役立てます。
よって答えは3になります。
77 日本における政府開発援助<ODA>の実施機関として正しいのはどれか。
- 国際協力機構<JICA>
- 世界保健機関<WHO>
- 国連児童基金<UNICEF>
- 国連世界食糧計画<WFP>
JICAは技術協力、有償資金協力、無償資金協力の援助手法を一元的に担う、日本における総合的な政府開発援助の実施機関です。
日本は、国連世界食糧計画 (WFP)、国連開発計画 (UNDP)、国連児童基金 (UNICEF)、世界銀行 (IBRD)、アジア開発銀行 (ADB) などの国際機関に資金を拠出して、多国間援助のODAを行っているが、これらは国際機関です。
よって答えは1になります。
78 災害に関する記述で正しいのはどれか。
- 災害時の要配慮者には高齢者が含まれる。
- 人為的災害の被災範囲は局地災害にとどまる。
- 複合災害は同じ地域で複数回災害が発生することである。
- 発災直後に被災者診療を行う場では医療の供給が需要を上回る。
災害時の要配慮者とは高齢者、障害者、難病患者、乳幼児、妊産婦、外国人などが含まれます。
人為的災害の被災範囲は広範囲にわたります。
複合災害とは複数の現象がほぼ同時または時間を置いて発生することによって起こる災害をいいます。地震が発生した後に津波がくることは複合災害の事例のひとつです。
発災直後は医療の需要が供給を上回ります。
よって答えは1になります。
79 血漿の電解質組成を陽イオンと陰イオンに分けたグラフを示す。

矢印で示すのはどれか。
- ナトリウムイオン
- カリウムイオン
- リン酸イオン
- 塩化物イオン
- 重炭酸イオン
血漿中、最も多い陰イオンは塩化物イオンになり、その次に多いのが重炭酸イオンになります。
よって答えは5になります。
80 血液中のカルシウムイオン濃度が低下した際に、ホルモン分泌量が増加するのはどれか。
- 膵島
- 甲状腺
- 下垂体
- 副腎皮質
- 副甲状腺
副甲状腺ホルモンは、血液のカルシウムイオン濃度を増加させるように働き、逆に甲状腺から分泌されるカルシトニンはカルシウムイオン濃度を低下させるように働きます。
よって答えは5になります。
続き

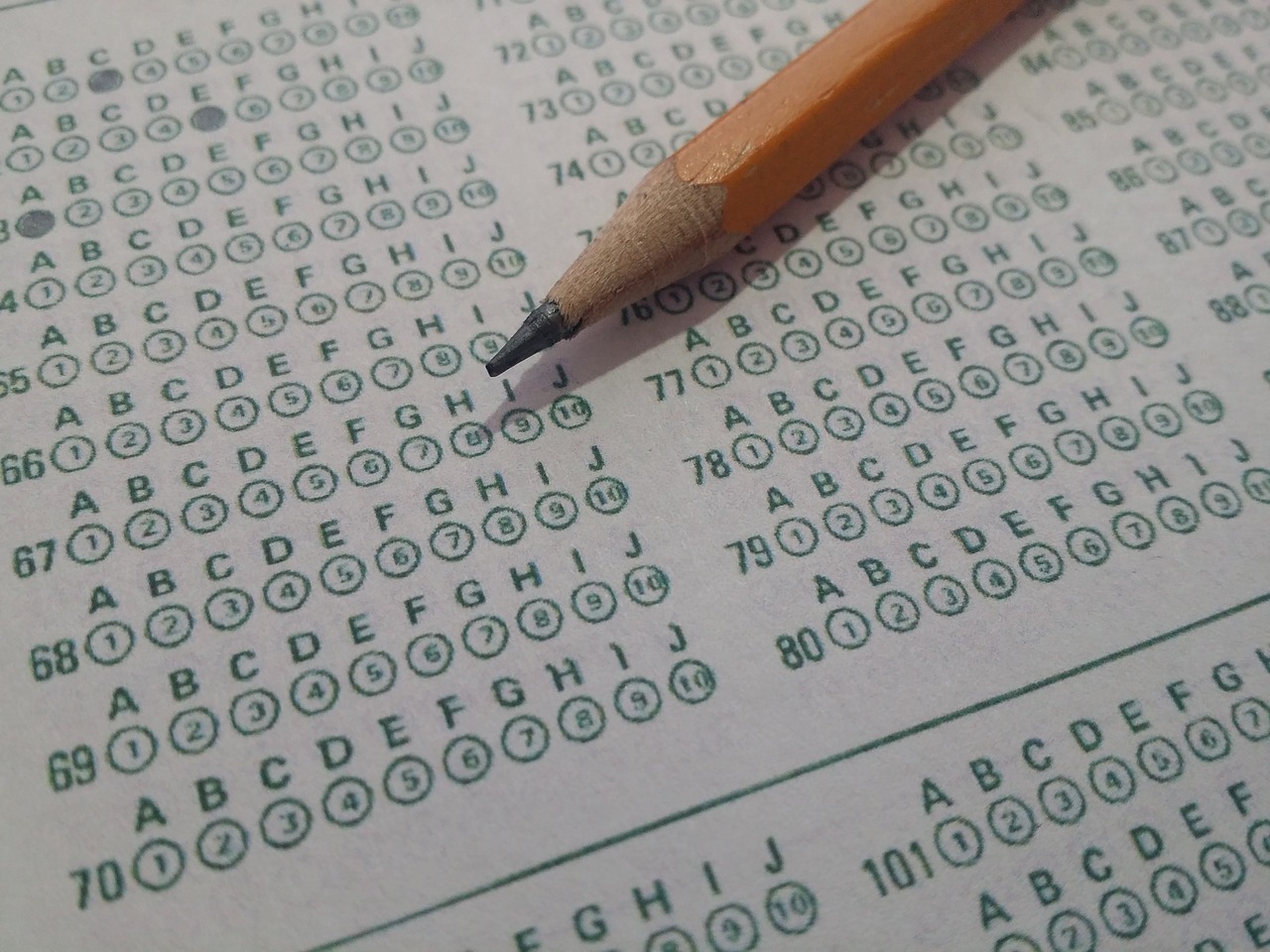


コメント